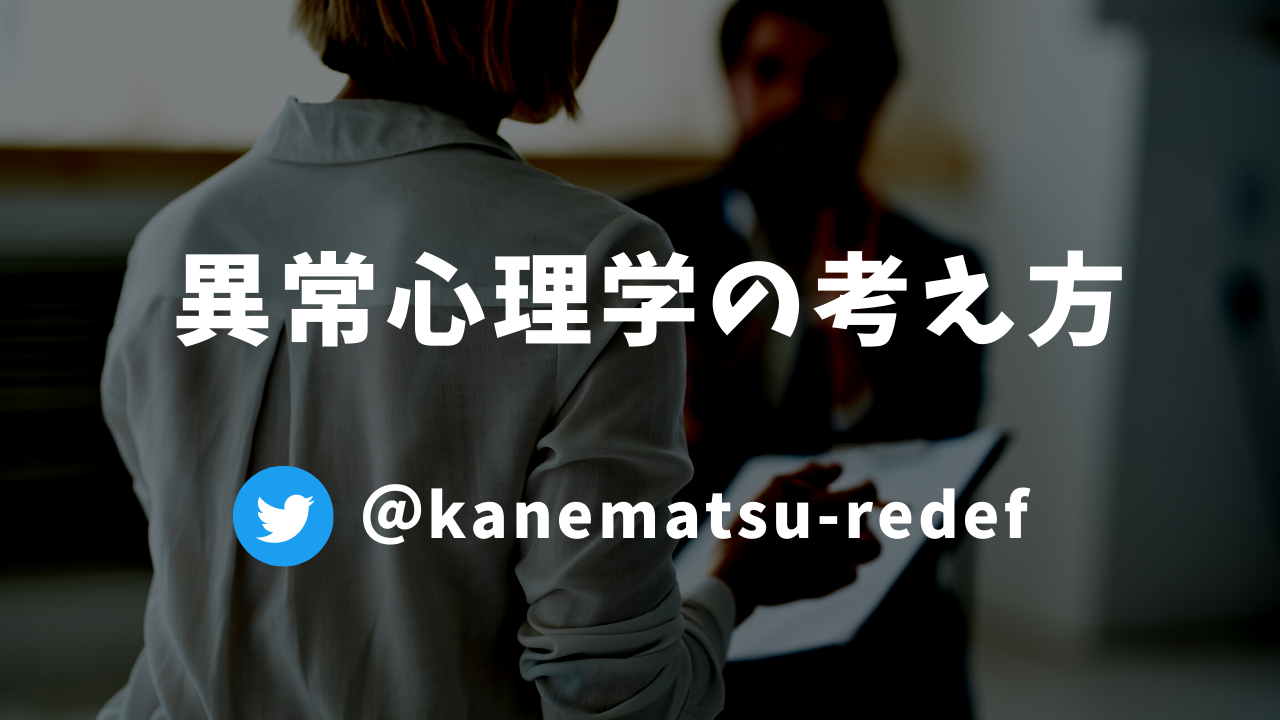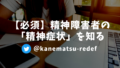【研修】就労支援事業所で使える「異常心理学」の考え方
こんにちは!就労支援事業運営.com、管理人のまつやん(@kanematsu_redef)です。国内で、就労支援事業所の開業・経営支援を行っています。近年、障害者総合支援法の制度変更の傾向により、職員の資質向上や事業所としての福祉貢献度が事業所評価に直結するようになりました。「研修」シリーズでは、障害者と接する支援者が知っておく必要がある障害者に関する知識を発信していきます。
今回は「異常心理学」について考えたいと思います。心理学の世界では、発達心理学、認知心理学など、様々な学問があります。異常心理学も学問の一つです。異常心理学の考え方を確認し、就労支援事業所の現場に生かしていきましょう。
異常心理学とは
心理学における学問の一つです。心理的な異常をテーマにしており、「心の異常はなぜおこるのか」「どのようなきっかけでおこるのか」を追求していきます。「異常」と「正常」の判断基準やアセスメントの方法、心理面が原因となって起こる異常行動などが、追求されるテーマとなります。
「異常」と「正常」の基準は?
判断の基準には様々な考え方があります。中でも、適応的基準、価値的基準、統計学的基準、病理的基準という4つの基準が代表的です。それぞれ見ていきましょう。
適応的基準
正常:社会に適応できている状態
異常:社会での生活に支障をきたし、円滑に過ごせていない状態
▼判断方法
周囲とのギャップを確認して客観的に判断「社会的判断」と障害者本人が自分で判断する「主体的判断」があります。
価値的基準
正常:法律や社会通念上のルール内で行動している状態
異常:法律や社会通念上のルールから逸脱して行動している状態
▼判断方法
価値的基準の中でも、社会通念に基づく判断を「生活的判断」といい、法律などに基づく判断を「理論的判断」といいます。
統計学的基準
正常:集団の中で平均値に近い標準的な状態を正常
異常:平均値から大きく逸脱している状態を異常
▼判断方法
定量的なアセスメントを行うことができるデータ指標に基づいて実施されます。
病理的基準
正常:病理学に基づいて異常所見が見られない場合に正常
異常:病理学に基づいて異常な所見、検査結果等が見つかった場合に異常
▼判断方法
医師が精神医学に従った考え方の中で判断します。
留意点
本来、就労支援事業所の障害者を支援する場合には、「異常」と判断できる言動に対して原因を追求します。逆に、「正常」な能力・行動は本人の強みとして捉えることで、職場適性や就労スキルの向上に応用します。ただし、様々な判断基準があるなか、判断の信頼性を確保するためには、障害者の経歴・家族歴、障害の診断経緯(現病歴)など、過去の生活プロセスを総合的に捉える必要があります。目の前で確認した1つの事象に限定した判断を行わないよう、常に網羅的に情報を収集しましょう。
まとめ
異常心理学についてお伝えしてきました。一般的に「異常」と「正常」の判断は難しく、属人的になったり、他者からの意見(主治医など)に終始したりしがちです。判断基準を理解することで、日々のアセスメントの着眼点が変化します。特に、定量性に優れた事実確認を行うことで、他者との比較から障害者の特性を評価することができます。比較を通じて、本人の心理的な異常を捉え、その個性に合わせた追加のアセスメント、支援方法の在り方を検討することが個別性の高い支援に繋がると考えています。是非普段の支援に活かしていただければ幸いです。
就労支援事業運営.comでは、国内で就労支援事業所の開業・運営支援を行っております。興味のある方は、お問い合わせください。最後までご覧いただきありがとうございます。
LINEで無料相談を実施する
LINE相談は福祉スタッフの皆さんとの出会いの場と位置付けております。生きた現場課題に触れることが、情報発信に重要と考えておりますので、是非お気軽にご活用いただければ幸いです。